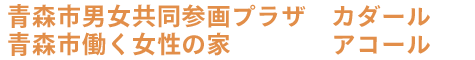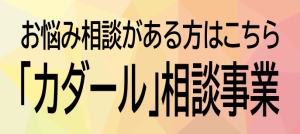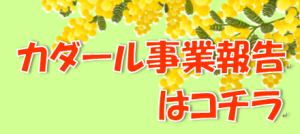令和4年度 アコール事業報告一覧
※新型コロナウイルス感染防止対策について
アコールでは、座席の減数、入室毎の手指消毒のお願い、消毒液の設置、
注意事項を記した案内板、参加者へのマスク着用の呼びかけなどの対策を講じ、 三密にならぬよう開催しております。
| 令和4年度「サークル体験講座」(後期) |
|
~フラワーアレンジメントサークルあおもり~
「手作り仏花で仏壇を華やかに」
日時:3月11日(土) 10:30~12:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
講師:小林 聖子さん(フラワーアレンジメントサークルあおもり講師)
参加人数:7人(女性:6人 男性:1人)
材料費:3,000円
|
| 「男女共同参画プチ講座&アコールフェスタ振り返りワークショップ~来年度の開催に向けて~報告 |
|
日時:10月15日(土) 10:40~11:50
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
参加人数:15人(女性:14人 男性:1人)
講師:千田晶子(アコール館長)
男女共同参画に関する基礎知識を学び、理解促進を図ることを目的としてプチ講座を開催しました。また、アコールフェスタ次年度の開催に向け、より有意義で円滑な事業運営を図るための参考とするためにワークショップを行ないました。
【男女共同参画プチ講座】
①NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会について
②指定管理者「アコール」「カダール」について
③男女共同参画社会基本法
④青森市の取り組み
⑤ジェンダーについて
⑥ジェンダーギャップ指数
【アコールフェスタ振り返りワークショップ】
①4~5人のグループを作る
②ワークシートの項目に沿ってポストイットに記入
③机上の模造紙へポストイットを貼付け、意見交換
④意見を模造紙へ追加、記入
⑤発表
プチ講座は利用者会の代表者会議を利用し、普段アコールを利用している方々へ向け、男女共同参画社会が目指すものと拠点施設「アコール」「カダール」の役割についてなど、パワーポイントの資料をもとに講義を行ない、これまで以上になぜ男女共同参画社会が必要なのか、理解を深めていただきました。
その後、4~5人のグループになり、アコールフェスタ振り返りワークショップを開催。日程や準備、各コーナー等7つの項目を挙げて意見交換を行なったところ、良かった点の他に、改善や工夫する点などの意見が出され来年度の開催に向け、大変有意義なワークショップになりました。
|
| 人権理解促進講座 スマホ教室「人を傷つけないスマホのルール」報告 |
|
日時:10月5日(水) 10:30~12:30
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
参加人数:8人(女性:7人 男性:1人)
講師:佐藤暁子さん(Softbank青森中央店)
市民の人権意識啓発・向上を目的とし、SNSによる人権侵害の現状について紹介。広がり続けるSNSやスマートフォンのルールを知ることによって、人権を守る知識について、また現在のスマートフォンによって繋がることの利点と欠点について認識を共有し、これからの支援の在り方や協力できることについて学習することを目的として開催されました。
①講座「スマートフォン関する基礎知識」
パワーポイント資料をプロジェクターで映しだし、スマートフォンの基礎動作・名称に関する情報を共有。スマートフォンの契約がない方にはスマートフォンを貸し出し
②スマートフォンを使う上での注意点
スマートフォンはその名の通り「賢い電話」です。ガラパゴス携帯とパソコンの機能を持ち、アプリでいろいろな機能を使えるが撮影した写真には撮影日・撮影場所などあらゆるデータが入っている。YouTubeなどにアップされる際には個人情報が漏れないように気を付けなければならない。
③人権を守るための肖像権への配慮
スマートフォンで撮影した写真・動画には肖像権が生じる。断りもなくSNSにあげてはいけないし、あげる場合はぞの人物に確認をとらなければならない。
④自分に合った使い方について
スマートフォンで通話する場合、かけ放題プランを選んでなければ30秒で20円かかる。インターネットを使うものはTverなどの動画を見る場合思った以上の容量を使用している場合もあるので気をつけた方が良い。
LINEの設定段階で友達認定フィルターをしっかりかけておかないと、無関係な知り合いの知り合いにまで繋がってしまう→参加者の個人情報を守るための設定を指導。
⑤質問タイム
LINEのグループを作る際に気をつけなけらばいけないマナーについての質問あり→講師より、LINEの「既読」表示は2011年東北大震災時の安否確認利用のため加えられた機能であることを伝え「既読」がついたらすぐ返信をつけるためのものではないことを伝える。他、LINEグループの作り方、メンバーの追加の方法を指導。
 講師はSoftbank株式会社所属でスマホアドバイザープラチナランクを所有。契約とは一切関係なくスマートフォンの正しい使用法を普及することが職務とのこと。参加者のほとんどは「スマートフォンの使い方が今一つわからない」「こわくて触ることができない」と話したため、まずは基本的な使い方をプロジェクターに映し出し説明。参加者全員に予めスマートフォンを使用するうえで不安に思うこと・心配するトラブルについて聞き取りをし講師に連絡していたため参加者のニーズに合った講座が成り立ちながらも人権を守るためのルールを伝えることができたと思います。質問タイムでのやりとりで、参加者が肖像権や個人情報を書き込むことへの問題意識が低いことが分かり、現在の法律では肖像権は法律で守られるべきだと明記はされていないものの、日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が適用されることを伝え人権を守ることへの意識を高めることができたと思われます。 講師はSoftbank株式会社所属でスマホアドバイザープラチナランクを所有。契約とは一切関係なくスマートフォンの正しい使用法を普及することが職務とのこと。参加者のほとんどは「スマートフォンの使い方が今一つわからない」「こわくて触ることができない」と話したため、まずは基本的な使い方をプロジェクターに映し出し説明。参加者全員に予めスマートフォンを使用するうえで不安に思うこと・心配するトラブルについて聞き取りをし講師に連絡していたため参加者のニーズに合った講座が成り立ちながらも人権を守るためのルールを伝えることができたと思います。質問タイムでのやりとりで、参加者が肖像権や個人情報を書き込むことへの問題意識が低いことが分かり、現在の法律では肖像権は法律で守られるべきだと明記はされていないものの、日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が適用されることを伝え人権を守ることへの意識を高めることができたと思われます。
|
| 講師デビュー応援講座「一家に1つ!オーガニックハーブで作るMYスプレー」報告 |
|
日時:10月2日(日) 10:00~12:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
参加人数:15人(女性:14人男性:1人)
講師:澤野真希さん(AEAJ≪日本アロマ協会≫アロマインストラクター)
自身の持つ資格や特技を仕事とする活躍の場を求める女性を対象にした「講師デビュー応援講座」で初めての講座を開きたいと考える女性に広報での周知の方法や講座の組み立て方等、基本的学習と実践力を養う場を提供する目的で開催されました。
①精油について…精油=エッセンシャルオイルでアロマオイルなどの名前で販売しているものには合成香料もあるので注意が必要。
②精油を安全に使うための注意点説明…精油を直接肌に塗ったり飲んだりしない。下記に気をつける。妊産婦、お年寄り、治療中の方は専門家に相談してから使用する。
③オーガニックローズマリーのMYスプレー作り…無水エタノール(今回は岩手県でお米を発酵させ作られたエタノールを使用)10gにドライローズマリーを漬け込んだものに、オレンジスイート、ラベンダー、ペパーミント、ゆず。青森ヒバ、黒文字の6種類の精油の中から好みの物、または全ての精油を加え、竹の棒でよく混ぜる。精製水を加え更に混ぜ合わせ完成。

講座開催が初めての講師に、講座開催に必要な基本事項をサポート。広い年代の参加者を募集できるよう、講座内容を使用頻度が高く、需要の多い除菌スプレーとするよう助言。不明なことにはメールでいつでも応えられるよう対応。講座当日は緊張している様子ではあったものの、打ち合わせしていた講座内容を全て参加者に伝えることができたようでした。参加者の中にはご自分の畑に自生していた植物を持ち込み、どのようなハーブか尋ねる方もいましたが安定して答えることができていました。予定より早めに講座は進行していましたが、残った時間は参加者の感想を伺う時間にあてるようにフォローをしました。講師のハーブに関する知識の広さに参加者の信頼度も上がりアンケートの満足度も高かったです。講師はAEAJ認定アロマテラピーインストラクターの資格以外にも日本アタッチメント育児協会認定ベビーマッサージインストラクター・日本オーガニックビューティーセラピスト協会植物調合士等数多くの資格を持っているが今後も新しい資格に挑戦するとのことです。
|
| 講師デビュー応援講座「お茶会が楽しくなるトゥグントゥグン韓国語」報告 |
|
日時:9月23日(金) 10:00~12:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
参加人数:11人
講師:横山真理子さん(元大韓航空スタッフ・韓国語講師)
自身の持つ資格や特技を仕事とする活躍の場を求める女性を対象にした「講師デビュー応援講座」で初めての講座を開きたいと考える女性に広報での周知の方法や講座の組み立て方等、基本的学習と実践力を養う場を提供する目的で開催されました。
①韓国語の文化の紹介(韓国の受験事情・流行・食について)
②韓国文化クイズでおさらい
③韓国語で自己紹介(韓国語表から参加者自身の名前などを書きだす)
④グループワーク(韓国語で自己紹介)
⑤参加者が韓国語に興味をもったきっかけについて発言

タイトルのつけ方、開催日時の決め方、講座の組み立て方など講師と話し合いを重ね決め、使用する資料を内容に沿ってパワーポイントで作るための工夫を助言。口座を開催するために必要なことを実際の講座開催を通し学ぶ支援ができました。講師は前半こそ緊張し表情も硬かったが、参加者のグループワークのテーブルを回るうちにコミュニケーションもとれてきて、質問に対しても柔軟に応対することができていました。講師は韓国に留学したのち大韓航空スタッフとして勤務、韓国料理の研究を行ない、韓国でのリポーター経験もあるため、幅広い質問に答えることができていました。質疑応答の時間に安定した存在感をアピールすることができたように思います。参加者からは韓国語の学習を含めた韓国料理講座や韓国旅行を目的とした韓国語講座の開催を求める声が多く出ていました。
|
| アコールフェスタ共催講座「親子簡単クッキング教室」報告 |
|
日時:9月18日(日) 10:00~11:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」料理室
参加人数:8組15人(女性6人 男性1人 女児6人 男児2人)
講師:青森市食生活改善推進員会
男女共同参画社会形成のために重要なワーク・ライフ・バランスの実現に向け、子育てに参画しながら女性が働き続けられる環境・社会をつくるべく、地域の子育て・学習機会の提供を通じ支援をすることを目的とし、家族一人ひとりが自分らしさを大切にしながら子どもの成長を見守りたすけるためのヒントを提供するために、「アコールフェスタ2022」2日目の10月18日(日)に開催いたしました。
◎メニュー
~ケチャップごはんおにぎらず ひじきごはんおにぎらず 牛乳かんてんパパゼリー~
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座前後に徹底した設備・調理用具・手指の消毒を行ないました。食材に直接手が触れないよう、保護者用・お子さん用のビニール手袋を用意し、食材も手指を消毒した講師が全てラップで個別に包装し準備していました。その他、左利きのお子さんが参加された場合を考え左利き用の包丁も準備されていました。
講座前に栄養素について簡単に教えていただき、成長期に必要な栄養について考えながら料理する大切さが伝わったように思われます。青森市内で全ての年代に向けての栄養教室や料理講座を主催している「青森食生活改善推進員会」のスタッフが2組の家族に対し1人以上の講師がつくように配慮され、保護者もお子さんも安心して受講することができたと思われます。
参加された方々からは「楽しく料理することができた」「またこの講座を開いてほしい」との声がけをいただくことができました。男児や父親の参加もあり、性別に関わりなく積極的に料理に参加しようという意識が徐々に浸透してきていることを感じさせられました。

|
| 令和4年度「サークル体験講座」(前期) |
|
~おしゃれな手芸~
「畳のヘリとメッシュで作る夏ポシェット」【2回連続講座】
日時:①6月29日(水) ②7月6日(水) 9:30~12:30
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
講師:大谷 真知子さん(おしゃれな手芸講師)
参加人数:①10人 ②10人
材料費:3,500円
~洋裁サークル~
「レッツトライ!Tシャツを作ってみよう」【2回連続講座】
日時:①8月23日(火) ②9月13日(火) 13:00~16:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
講師:川越 美保子さん(洋裁サークル・Mの会講師)
参加人数:①6人 ②5人
材料費:1,000円
|
「人権理解促進講座~地域の人権を守る民生委員の活動~」報告
|
|
日時:8月20日(土) 10:30~11:15
場所:青森市働く女性の家「アコール」会議室
参加人数:20人(内男性1人)
講師:前多 敬子さん(中央地区民生委員児童委員)
市民の人権意識啓発・向上を目的とし、地域の民生委員の活動を紹介。民生委員の活動を通し、人権を守る活動について、また現在民生委員が置かれている状況について認識を共有し、これからの支援の在り方や協力できることについて学習することを目的として開催しました。
①講座の趣旨について説明
②民生委員とは
・民生委員は厚生労働大臣から委託され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い社会福祉の増進に努めること。児童委員を兼ねている。(資料に基づき説明)
③民生委員の歴史について
・民生委員制度は第一次世界大戦中の1917年(大正6年)に岡山県で「再生顧問制度】として誕生。当時の岡山県知事の呼びかけで始まった。その翌年の1918年、大阪府で「方面委員制度」が発足。この制度が全国に普及し、のちに「民生委員」と改められ現在に至る。
④民生委員の課題
・ボランティアで活動する民生委員は、年々その数を減らしている(充足率の減少)。それと反比例し年間で1人の民生委員の訪問件数は平均167件(平成29年厚生労働省調査による)となっている。
⑤ミニ講座「民生委員って何?」(講師:前多敬子)
・民生員児童委員信条について
・日本が手を挙げないと援助が届きにくい。「こんなことを相談してもいいのか?」と相談することを迷っているうちに相談を諦めてしまうケースが多い。実情を把握することが大事なので、いろいろな集まりに出て声を拾い、包括支援センターや社会福祉協議会など適切な援助への橋渡しをしている。
⑥参加者より
・参加者でご自身が民生委員を長く続けている方より発言があり。担当している地区の民生委員は年間250日、平均して1ヶ月20日間以上の訪問を続けている人もいる。75歳以上の方だけで構成されているご家族には「避難行動要支援者避難支援制度」を周知し、命を守る制度があることを知っていほしい。
受講者は、民生委員の存在は知っているものの、その活動については知らないという方が多かった。アンケートの記述には、「民生委員について、まるで知らなかったのでとても参考になりました。」「知っているつもりでスルーしていることが、かなりあり気付くことができました。ありがとうございます。」とあり、アンケート満足度も全て「満足・ほぼ満足」でした。民生委員の活動を紹介する講座を通し、地域の人権を守ろうという意識が高まったと思われます。参加者の中には人権擁護委員の活動をされている方もおり、人権についてもっと広めていく場を作りたいというご意見をいただきました。これからもこのような場を設け、活動の場を広げていくことにより、民生委員の活動や人権に関する意識の啓蒙・向上であろうと手ごたえと、これからも継続していく必要性を感じることができました。
|
「双方向階段ギャラリー『育児介護休業法と女性活躍推進法改正のポイントについて』」報告
|
|
日時:①7月6日(水) 11:20~12:10
場所:青森市働く女性の家「アコール」談話室
参加人数:9人(内男性1人)
ファシリテーター:長内美子
女性のエンパワーメント推進のための環境を整えるため、地域社会のリーダー的活躍をされている方々に働く女性の現状と社会環境について啓発をおこない、女性が働き続けるためには男性の家事・育児・介護参画が必要であることの理解を深めていくことを目的として開催しました。
階段ギャラリー(7/2(土)~7/24(日)開催)の「女性が働きやすい社会を考えるパネル展」で、令和4年4月1日より改正となった育児介護休業法と女性活躍推進法の改正ポイントについて展示し、その内容に沿っての講座となりました。
①講座の趣旨説明
②令和4年4月1日改正の育児・介護休業法のポイントについて
③令和4年10月1日改正の育児・介護休業法のポイントについて
④令和5年4月1日改正の育児・介護休業法のポイントについて
⑤令和4年4月1日改正の女性活躍推進法のポイントについて
⑥育児休業の取得について考えてみましょう
⑦参加者一人ひとりの意見発表
⑧まとめ
現役で仕事をしている方の参加は少なかったものの、参加者は全員真剣に働く女性の現状について耳を傾けてくれました。全員内容を聞き漏らさぬようにメモを取り、時にが説明を求める姿が印象的でした。ワークショップの後半、育児休業を取得しやすい職場づくりについて話し合った際、「コミュニケーションがとれていること」「仕事の分担がうまく機能し、だれが休んでも交代できること」「上司が把握する能力・部下が将来自分が上司になることを考え職場環境の改善に参画すること」等の意見が出されました。新しい知識を得ることができてよかった、との感想をいただいたので、これからも育児・介護・女性活躍に関する新しい情報を発信していきたいと思いました。
|
「ママパパ&ベビーのタッチでなかよし」報告
|
|
日時:6月5日(日) ①10:30~12:00 ②13:30~15:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」託児室
参加人数:①3組9人 ②1組3人
講師:丹羽 春美さん(英国IFPA認定アロマセラピスト・ベビーマッサージ指導者)
例年は「ママとベビーのタッチでなかよし」として人気の高い講座ですが、今回は男性の家庭参画を促進するきっかけを提供できればと、父親と母親で参加する形をとりました。
子どもと2人きりでいる時間の長い母親だけではなく、赤ちゃんと接する時間が短い父親も参加したことにより、赤ちゃんに触れる時に適した力の入れ方や目を合わせて接することが大切なことを学ぶことができました。
初めは講師に促されても赤ちゃんに触れるだけだった父親も、力具合を講師から指導されているうちに、童謡を口ずさみながらリラックスしてマッサージを行なっていました。父親自身に対するリラックス効果や愛情ホルモンセロトニンの分泌があることを教わり、家庭でも継続して育児に携わりたいという意識を高めることができたと思われます。同じような月齢の赤ちゃんや親と接する時間を持ったことで共有意識とリフレッシュ効果を得られた様子でした。満足度も「満足」と回答をいただきました。
担当者より、育児の悩みを共有し情報を交換する場としてアコール利用を提案したところ、育児中の友だちに声がけしたいとのことでしたので、サークル育成が可能であるなら支援していきたいと考えています。

|
「男性の料理入門講座『おべんとう作り編』【2回連続講座】」報告
|
|
日時:①5月26日(木) ②6月2日(木) 18:30~21:00
場所:青森市働く女性の家「アコール」料理室
参加人数:①6人 ②7人
材料費:1,600円(2回分)
講師:青森市食生活改善推進員会
例年人気の高い講座ですが、今回は基本的な料理の知識だけではなく、「おべんとう」という一歩進んだ形で食への関心、料理を作りことへの積極性が生まれることによって、家事への参加意識を高めることを目的として講座を開催いたしました。
①5月26日(木)
◎ごはん 豚肉のみそヨーグルト焼き アスパラベーコン巻 フライパンで貝焼きみそ ひじきの煮物
1回目は、ご飯の炊き方、切り方の種類、食中毒に配慮した調理法、調理器具の説明などの基本を学びます。
控室で調理の手順の説明後、感染症対策として徹底的に手指・手首を洗うことを指導。資料を基に切り方について丁寧に説明し、旬の野菜や料理法について学びました。
料理が女性だけの仕事ではないことを伝え、お弁当ひとつを作ることにどれだけの工程が必要かを知ってもらうことができました。同じ料理の初心者同士で楽しく料理をすることで、男性が料理をすることが当然のことであるという認識が生じ、これからも積極的に家事に参加していく意識が生まれたと思われます。
②6月2日(木)
◎ごはん 焼き魚 シャキシャキ長いもと豆腐のふんわりつくね ちくわきゅうり 厚焼き玉子
小松菜のなめたけ和え 人参とキャベツのしりしり
2回目は、ご飯の炊き方、野菜の切り方、日持ちする食材の活かし方、調理方法の説明など和食の基本を学びます。
メニューを見た途端「こんなに作れないのでは?」と話す参加者がいたが、効率よく順番を考え、時間内に調理することでバランスの良い副菜を多く入れたお弁当作りが可能であることを実感し、感嘆している様子でした。
家事も同じで、工夫することによって短時間で暮らし方が楽になることをお伝えすると家事参画の意欲がわいた様子でした。
講座終了後、講師に「お菓子作り講座をやりたい」「イタリアンの料理講座をやってほしい」との要望が出されました。料理で自信をつけることにより家事参画への扉が開かれる手ごたえを感じられました。
 
|